

| 過去の日記 | 2003年12月分 | 2004年1月分 | 2004年2月分 | 2004年3月分 | 2004年4月分 | 2004年5月分 | 2004年6月分 |
| 2004年7月分 | 2004年8月分 | 2004年9月分 | 2004年10月分 | 2004年11月分 | 2004年12月分 | 2005年1月分 | |
| 2005年2月分 | 2005年3月分 | 2005年4月分 | 2005年5月分 | 2005年6月分 | 2005年7月分 |
当ホームページを立ち上げて8年目を経過、沢山の方よりアクセス頂き管理人の私も大変嬉しく思います。 ★幼稚園は年間を通して時季の園行事が盛り沢山。 毎日園内では子ども達の楽しい姿を私たち保育者は指導しながら共に楽しんでおります(笑)。 二度と戻れない幼稚園生活を大切に考え、園長の私が直々に園児と接したことを日記に綴ります。 この「毎日わいわい日記」は、正に山王の保育内容が解る保育日記として、 この楽しいひとときを皆様に観て頂こうと作ってみました。 園長 小倉隆夫 |
8月 |
![]()
8月31日「他園との交流 パート2」     ←SLバス ナンバーはニコニコ(2525)^^ ←SLバス ナンバーはニコニコ(2525)^^●夏休み最後の日、もう1カ所の幼稚園見学に足を運んだ。 私と同じ2代目園長先生は年齢も30代半ばと若く、バイタリティ溢れるフレッシュ園長先生である。 既に8月23日から2学期は始まっていて、園庭では園児たちが遊んでいる姿も見ることが出来た。 保育内容は一斉保育で山王とほぼ同じ方針でおこなわれ、中規模園の特色が多く感じられた。 例えば、なんと大きなお風呂が設置されクラス毎お風呂に入るのである。 汗を流してサッパリしてから昼食を食べるなんて羨ましい。(マンモス園では到底不可能なこと) また、物に対する既成の概念にとらわれず、暖かみのある手作りを職員一同でおこなっている。 園だよりは月に一回クラス毎の冊子で作成、しかもカラーページ。行事終了後は、担任はもとより父母からも 感想をもらい掲載する。内容の濃い素晴らしい園だよりである。 写真のキティちゃんは、先生達による手作りボード。ベニア板に下絵を描いて色はな紙を使って敷き詰めていく。 これは毎年デザインを変えて製作し、運動会々場に展示するとか・・・・・・(驚) その他書ききれないほどユニークな仕掛けを考えている園長先生はすごい!! 園長先生と記念撮影させてもらい、園を後にした。 |
8月28日「パパの会バーベキュー」        ●父親の子育て参加を助長するパパの会では、昨日泉の森ふれあいキャンプ場において、父親と子どものみ40名集まり盛大におこなわれた。 天候にも恵まれ、木々の間から薄日がさす程度で絶好のバーベキュー日和であった。 お母さんのいないバーベキュー会は、すべて父親が設営から買い出し・調理、子どもの面倒・後片づけまですべておこなわなければならない。 従って子ども達はパパを頼って一日過ごすことになる。 子ども達はアスレチックで遊んでから、焼きたてのお肉を食べ、食後はスイカ割り・当てくじゲームで盛り上がり、最後はかき氷を食べたりと 夏休み最後の思い出がまた一つ出来たことでしょう。 パパさん達、ご苦労様でした。 |
8月26日「年長 スイカ割り」      ●台風11号の影響で園庭で予定していたスイカ割りは雨天の為、ホールでおこなうこととなった。 まめしぼりで目隠しして竹刀を持ち、おそるおそるスイカに向かって・・・・“そこだよ〜”“エイ!” 男児は割りたい一心で力強く叩いていた。今年のスイカは表皮が硬いのか、散々叩き付けられヒビは入るが真っ二つに割れることはなかった。 大玉のスイカ(山形産)は終了後、教室で食べた。とてもみずみずしく甘いスイカ美味しかったね。 |
8月24日「夏休みの思い出を自由画に」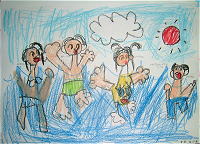   ●夏季保育中に、各クラスで夏休みで一番思い出に残った出来事を描かせてみた。 海水浴や遊園地・おばあちゃん家など、ご家族の皆さんが主役となって表現されていた。 園児が描いた絵は完成すると、担任が一人一人説明を聞いて登場人物や場面を簡単に記していた。 クレヨンで描いた画からは、実に豊かな情景が湧き出ている。    “みんなで大きなホテルに行ったんだ” “自転車を一人で乗れるように練習したの” 余程楽しかったんだね〜。 |
8月19日「35年を経て、園服をリニューアル」    ●上着は紺色・ズボンスカートはグレー色・カバンは黄色のショルダーで長年親しんできた園服を来年度よりリューアルする。 現在の制服は長きに亘って愛用されてきたが、時代の移り変わりにより食生活や生活様式も変化し幼児の体格は確実に大きくなった。 それに伴いブラウス・ズボン・スカートだけを替える方策(小変更)も考えられないこともないが、 如何せん30年以上経過、タイミング的にはモデルチェンジの時期ではと判断した。 一昨年、私が園長就任する前から、制服業者4社の展示会に出向き検討を進めた。 新規採用するにあたり私の考えとしては「清楚で清潔感がある・着用感は着易くシンプルで機能的・ 新しい山王のイメージを持った存在感・価格は出来るだけ抑える」 このことを踏まえ検討に入った。 今までの制服から大きな変化は、 1.帽子とリボンの廃止。 2.半袖ブラウスを含む、男女共有のブラウスを採用。 3.ズボンとスカートは吊りからウエストゴムに変更。 4.衣替えの概念を見直し夏服を廃止し、あわせて麦わら帽子から白地ピケ帽子に変更。 5.遊び着を見直しスモックを変更、6月1日頃からブラウス通園となりサマーエプロンを採用。 6.ショルダーカバンからリュックカバンに変更。 以上6項目が大きく変わったところである。 帽子を廃止する理由としては、本来は頭を守る保護として有効ではあるが、園児の7割強はバス通園を利用し、 乗車内では帽子のつばが大きく園児の顔色等観察しづらい。徒歩通園は自転車通園が多く、 今後同乗者はヘルメット着用の義務化が進むようである。 また女児の場合、髪型によっては髪留めゴムが邪魔をして帽子が被れず意味を成していない。 当然ながら登園後の外遊びでは紅白帽子は着用させる。6月〜9月までは日差しが強いので白地ピケ帽子を着用する。 丸襟角襟に男女分けていたブラウスは丸襟に統一し、赤いリボンの代わりにブラウス中心部がデザイン意匠に よって引き締まって見える。長袖の袖もとはボタンからゴムになっている。 男児の吊りスボンは、トイレの際に面倒を強いられていたので、ウエストはゴムになっている。 体系的にどうしても吊りを希望する方にはオプション設定もある。 ショルダーカバンは落ち着いた質感のあるリュックに変更、幼児用水筒も入るので両手が自由になる。 男児のズボンの裾丈は、下着(トランクスパンツ)がはみ出さない丈になっている(笑) 女児のスカートはプリーツからボックス型に、ウエストが締りバランスの取れたデザインを施している。 最後に、ご兄弟の方や知人から譲り受けた現行の制服は、そのままご利用いただいて構いません。 3年間程度は新旧の制服姿があっても宜しいでしょう。 |
8月10日「他園との交流」 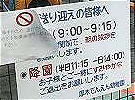 ●夏休みに入ると、私は好んで他の幼稚園へ見学に行く。何事にも興味を抱き、行動することは大切だと思っている。 昨日は厚木市内にあるD幼稚園を訪問した。 園長先生とは10年以上前から青年会議所活動を共にしていたが、同業者であってもなかなか仕事の話をする機会に恵まれなかった。 今回タイミング良く、時間を設けていただいた。 創立は昭和40年、平成3年に新しい園舎を建て替え、とても明るい雰囲気の園舎、園庭も広く隣には駐車場が完備されていた。 驚いたことに駐車スペースは120台止められるとのこと。周りが田畑で、地主さんに理解を求めて少しずつ土地を買収して実現、何とも羨ましい。 保育内容はほぼ同じ方針で、一斉保育を基本に15クラス(年長6・年中6・年少3クラス)で園児数406名。 園長先生とは年齢も近いとあって、経営に対する考え方・充実した保育の進め方には協調する部分も多く、良いと思ったことはお互いに吸収し 採り入れていこうと話がまとまった。最後に私がプランしているプロジェクトにも賛同してくれた。(秘)^^ 「今度山王さんに行かせてもらうよ」「どうぞいらしてください、お待ちしています」 |
| 8月1日「初代園長、山王幼稚園への思い エピソード1」 ●今年で幼稚園創立35周年目を迎えた。 昭和46年3月に神奈川県から公認を承けて4月に第1回入園式をおこない全園児82名のスタートであった。 山王幼稚園が産声を上げたのは、この下鶴間地域に幼稚園がなかったこともあって、初代園長が小学校の教員をしていたこと、 代々農家だったので建設予定地(畑)があったという条件で、園長は苦渋の決断に至ったのだ。 昭和44年頃から幼稚園設立プランを打ち出し、 当時深見小学校の教師であった初代園長は校長先生に“2年後に幼稚園を設立することにしました。 よって低学年1年生の担任を2年間させてください” 園児に一番近い年齢児童と過ごしたく直訴したのである。 教鞭をとっている間も、神奈川県へ設立申請の為膨大な書類を一人で作り、 予定地の青写真を練り上げ、もちろん建築設計士との打ち合わせを重ねる毎日だったようだ。 長男である私はその当時中学生、毎日クラブ活動に追われ、親の考えていることなど関心は全くなかった。 ただ今思い出すことは、夕飯後テーブルに紙と色鉛筆を用意して、何通りかの鶴を描いて二人で話し合っていたことを思い出す。 これは園章を考えていたのだ。 建設予定地(現在の園庭)には、木造のL字型平屋の園舎(一部職員室は2階)が着々と工事が進む中、最低基準値の遊具の設置や、 送迎バスの購入、自ら運転するためにマイクロバスの運転免許を取得したようだ。 そして現在まで続いていた制服の選定。 最後に肝心な教職員の採用など、スタートさせるまでには山積みの課題をクリアしていけなくてはならなかったのだ。 つづく |